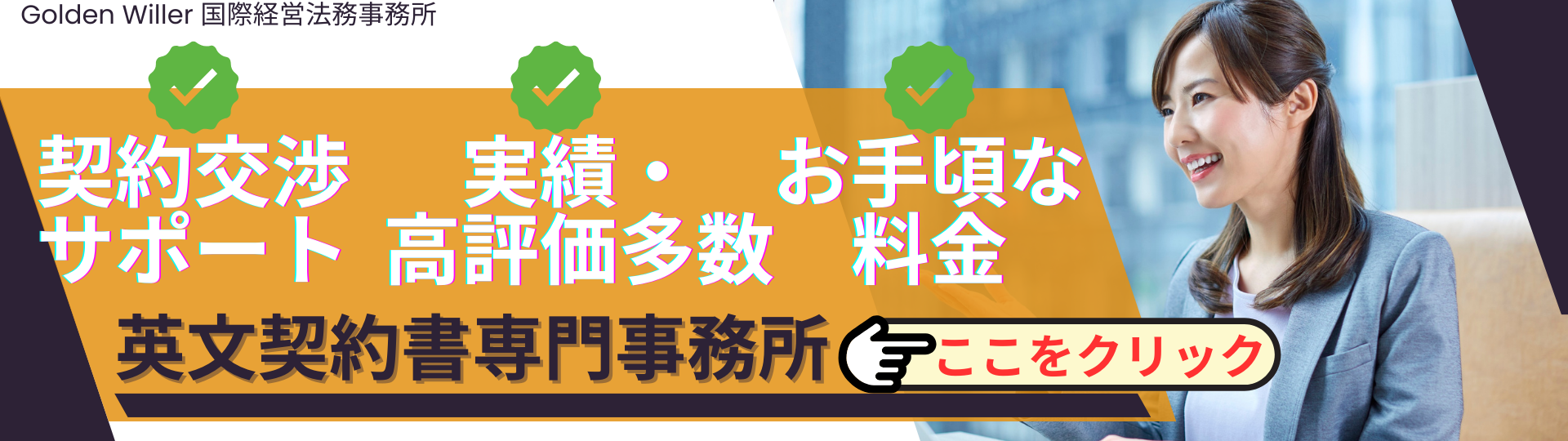契約書と代理人についてわかりやすく解説します
代理人の問題点
契約書には、当事者、として、自分と取引の相手側とが表示されます。
自然人同士の契約であれば、当事者として表示する者に迷うことは少ないでしょう。
ですが、それが、会社形態や財団、社団等の法人、組合、宗教法人、権利能力なき社団であれば、適切に表示しなければ、後々の紛争を生じる原因になりかねません。
また、契約の本人ではなく、代理人と契約を締結する場合もあるでしょう。
未成年者や、後見人、被保佐人、使用人、支配人等も問題となります。
ですが、その者は、本当に本人の代理人でしょうか。
本当にその契約を締結する権限を持っているでしょうか。
代理人と契約そ締結するときの注意点を解説しています。
以下、契約書と代理人について、見ていきましょう。
契約を代理人と行う場合
日本の民法上では、代理人は本人のために行動し、その法律効果は直接本人に生じるとされています(民法九九条一項)。
この規定があることによって、代理人との間で安心して、契約を締結することが出来ます。
ですが、後述するように、無権限で代理人と表示して、取引をし、目的物や金銭を持ち逃げされることも多々あります。
契約を代理人と行う場合には委任状を確認する
では、代理人に適法な代理権があるかどうかの判断はどのようにするのでしょうか。
それは、委任状の有無で判断することになります。
法定代理 人の場合は戸籍謄本など公的な書面で証明 がつきますが、任意代理人の場合は、委任状によってのみ代理権の有無を判断できることになります。
この委任状を契約 書につけて一体とさせれば、契約書に本人 が記名押印、あるいは署名したことと同じ 証明力が生じます。
契約を未成年者と行う場合
未成年でも当然、法律行為を行うことは可能です。
ですが、未成年は判断力においてまだ未成熟であるので、その範囲が制限されています。
この制限は、父母による取消権として民法上規定されています(民法四条)。
父母は共同して子の代理人となります (民法八一八条三項、八二四条)。
契約を後見人と行う場合
では、未成年において、父母がいない場合はどのように契約するのでしょうか。
父も母もいないか、あるいは親権を行な うことができないときは後見人が法定代理 人となります。
後見人は、被後見人の財産の管理権と被 後見人を代表する権限があります(民法八 五九条一項)。
これは、家庭裁判所が選任するか、遺言によります。
後見人がつくのは未成年者だけではあ りません。
精神状態が良好で無い人について、家庭裁判所が後見開 始の審判をしますと(民法七条)、成年被 後見人として後見人がきめられることにな ります(同八条)。
契約を被保佐人と行う場合
被保佐人という制度があります。成年被 後見人ほどではなくても判断力の劣る状態 となった人のための制度で、これも家庭裁 判所が保佐開始の審判をします(民法十一 条)。
保佐人は法定代理人にはなりません。
一定の重要な行為、たとえば借金をするこ と、不動産を処分することなど(同十二条 一項)の場合、保佐人の同意がないと、あ とで取り消されるという心配があります。
したがって、被保佐人と取引をする場合に は、保佐人の同意書をもらうか、契約書に 同意の趣旨を記入してもらい、書名(また は記名)押印をしてもらう必要があります。
契約を使用人と行う場合
会社が当事者の場合に若干説明しました が、雇われている使用人が、会社 または事業主を代理して契約などの法律行 為をすることは通常です。
これも代理人の一種です。
営業に 関しては一定の事項について代理権限があ るとされています(商法二五条一項、会社 法一四条一項)。
法律によって、その代理権が規定されていますので、その使用人の表示さえしっかりしていれば契約書上の権限は問題ありません。
契約を支配人と行う場合
支配人という表示は、その支店の権限の一切が帰属しているという印象を受けます。
そして、支配人には、登記を経たもの(商法四十条)と、登記を経ていないものが存在します。
登記 した支配人は、非常に広い範囲の代理権を 持っています。
支配人はその関与している営業について は、一切の行為について営業主を代理する ことができるのです。
裁判までできる、というのは非常に広範な 代理権があることになります。
また、支配人の代理権に制限を加えても、こ のような制限を知らないで契約した相手方 に対して、その制限を対抗することはできません。
したがって支配人の営業に ついては、安心して支配人と取引契約を結 ぶことができるのです。
また、本店や支店の営業の主任であると示すような名称 を使っている使用人は、商法上の支配人と 同じような権限を営業主から与えられてい るものとみなされます(商法二四条、会社 法一三条)。
登記のある支配人と契約を結んだこととはほ とんど扱いが同じになります。