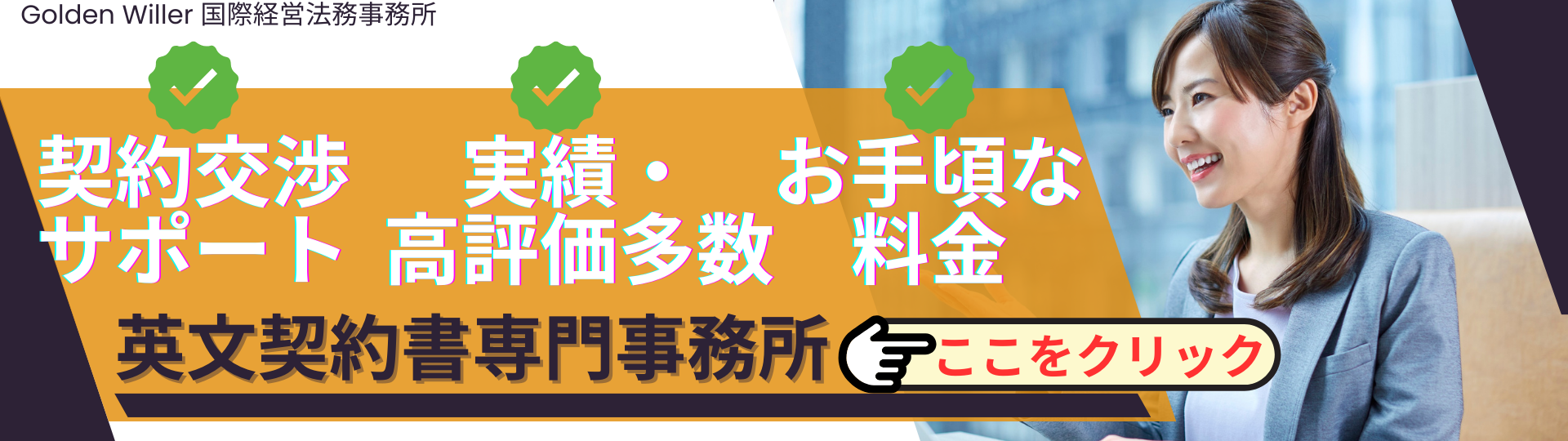契約交渉を行う場合のポイントをわかりやすく解説します
契約書と契約交渉について
あまり身近とは言えませんが、大きな契約を締結する場合には、いきなり契約書を作成するのではなく、契約交渉が数度行われます。
この契約交渉は、お互いが自分に有利になるように交渉する場ですが、そこでも一定の注意点は存在します。
そこで、契約書を作成する際の契約交渉についての注意点を解説しています。
契約交渉を行う場合のポイント
主張内容は明確に記載する
国内での契約交渉では、大まかな部分について合意し、後の些細な部分については順次協議に基づいて決めていきましょうという方法が採られることが多いと思われます。
英文契約書では、あまりこのような取り決めは行われません。
出来る限り、その取引から想起される事項については、交渉を行い、契約書に具体的に落とし込んでいきます。
特に、取引に慣れている企業であれば、自社に有利な契約書をあらかじめ作成しておいて、それを相手方に提示し、契約してしまいます。
提示された側がそのままその契約書にサインすると、取引を行ううちに、相手方の有利な条項が多数あることに気づきます。
紛争になったときに一番実感することになります。
ですので、当該ビジネスモデルに関係する条項は、出来る限り契約が成立する前に、具体的な形で、契約書に記載していくことが重要です。
商品の数量と代金額は明確に記載する
また、商品の数量と、商品の代金額については、随時、確定していく必要があります。
それは、商品の相場が変動することがあるからです。
商品額を変更する場合には、相手方からの承諾期間に期間を 設ける等の対策が必要です。
なぜなら、商品額の引き上げを申し込んだが、相手方から返事が無いので、交渉がストップしたままにしておいたら、半年後に、提示額より商品の価額が急騰しており、突然、相手方が、承諾してくるという事例もあるからです。
商品の数量についても、同じようなことが言えますので、注意が必要です。
交渉経過の保存
通常の売買契約等であれば、契約交渉の時間はそんなに長期になることはないと思います。
ですが、M&Aであったり、合弁事業であったりすると、その契約交渉は長期にわたることがあります。
このような場合には、口約束だけで進めてしまうと、現状の変化等により、言った言わないの水掛け論に陥りがちになります。
そこで、一つの交渉が進展すると、文書化し、記録に残るようにします。
そして、最後に、これらの文書をまとめて契約書を作成するようにします。