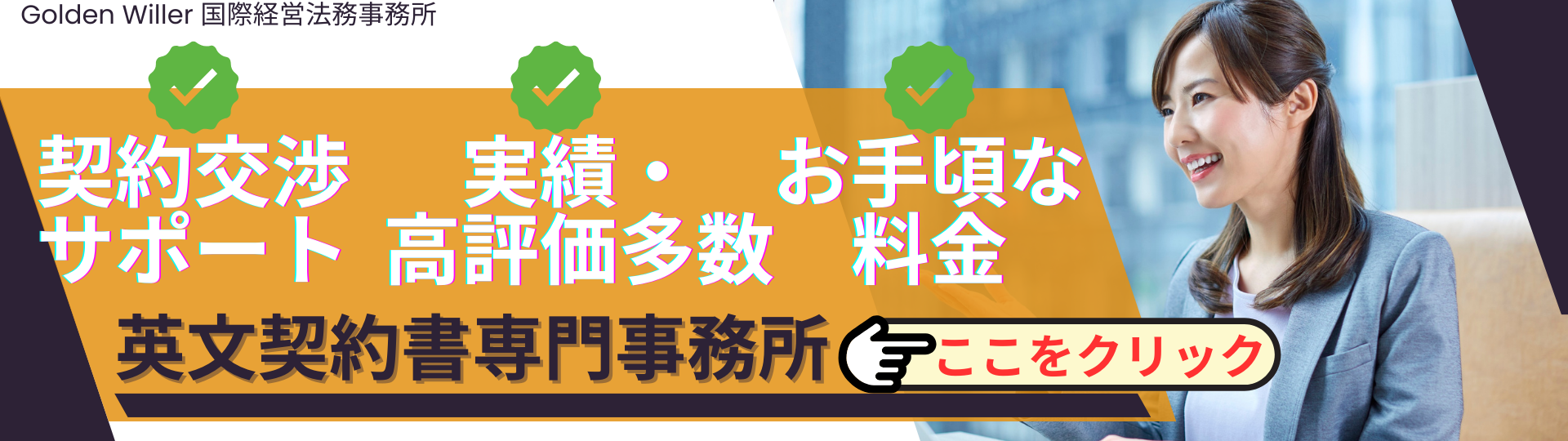英文契約書の「相殺条項(Set-off)」をわかりやすく解説します
相殺条項(Set-off)について
簡便な決済方法
様々な取引において、両当事者がお互いに持つ債権を同じ金額の範囲で相殺することは、簡便な決済方法として頻繁に利用されます。
相殺が不利になる場合
相殺は簡便な決済方法ではありますが、現実に入ってくるはずの現金が入ってこないので、商品販売契約の売主からすると相殺を避けたい場合もあります。
また、商品の売買契約において、買主が、買主が購入した商品に瑕疵があることによって損害を受けたとして様々なクレームを主張し、その損害賠償請求額と商品の販売代金を相殺することもあります。
相殺条項の実際上の注意点
実際のビジネスでは、相手方当事者が持つ債権での相殺ではなく、相手方当事者の関連会社が持つ債権債務による相殺の主張が行われることもあります。
これは、法律的には債権債務は特定の人にしか効力がない相対効ですので、当事者以外の関連会社が有する債権債務を相殺適状にするには債権譲渡の手続が必要です。
ですが、商品売買契約の買主にしてみれば、出来る限り相殺を認めておくようにしようと、契約条項に、関連会社の債権債務を含めて相殺可能という趣旨の規定を置いている場合もあります。
また、相手方当事者の支払い能力が低い場合において、自社側が相手方当事者に対して別の債権を有する場合に、相殺によって支払いを確保するということもあります。
相殺禁止の条項
現金での支払いを望む当事者や、相殺を認めることによる法律関係の複雑化をさけるために、相殺禁止の条項を置く契約書もあります。
これらは、その取引内容や、自社が相手方に持つ債権債務の量、相手方の支払能力や信用状況によって、相殺を認めるのか、禁止するのかが変わってくるといえます。
以下では、相殺を禁止する条項例を挙げておきたいと思います。
◆英語の例文・書き方
(1)In the event of any claim being made by AAA against BBB, AAA shall not be entitled to withhold any amount due under this Agreement or any individual contract or to set off the amount of such claim against any amount due underthis Agreement or any individual contract.
(2) All such claims shall be settled separately.
◆日本語例文・読み方
(1)AAAがBBBに対して、請求を申し立てる場合、AAAは本契約または個別契約に基づいて支払わなければならない金額の支払いを保留する権利はなく、また、本契約または個別契約に基づいて支払わなければならい金額と当該請求額を相殺する権利はないものとする。
(2)かかるすべての請求は別途に解決されるものとする。