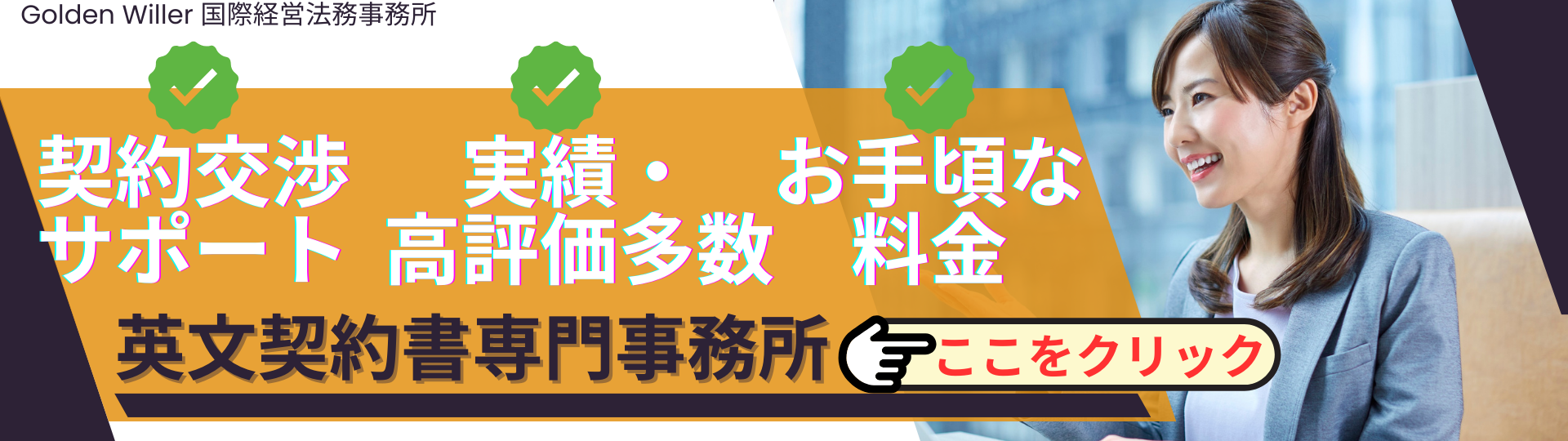契約の締結・契約自由の原則をわかりやすく解説します
契約が成立する時点はいつか?
契約が成立する時点はいつでしょうか。
これは、英文契約書でも同じ問題がありますが、原則的には、当事者の意思表示が合致したとき、といえるでしょう。
例外的に、保証契約等の場合に、契約書等の書面が必要な場合があります。
また、契約を締結する際に重要な原則としまして、契約自由の原則があります。
以下、契約の締結・契約自由の原則について、見ていきましょう。
原則の説明
契約の成立には、当事者の意思表示のみというのが、日本の民法の原則です。
売買契約(民法五五 五条)にしても、賃貸借契約(民法601条)にしても意思表示のみでの契約成立を規定しています。
それは、なぜかといえば、取引というものは、本人同士の自由意思によってのみ行われるのが原則だと考えることにあります。
これは、古代ローマ時代からの大原則と言えるでしょう。
この点から考えても、契約書というのは、基本的な機能としまして、裁判上での重要な証拠という位置づけになります。
そして、本人の自由意思によって契約が成立するということは、契約内容については、本人同士が自由に決められるということを表しています。
この原則がいわゆる、契約自由の原則、ということになります。
この原則があることからも分かるように、契約というものは、絶対的に本人同士の意思が重要であるということです。
例外の説明
しかし、例外として、つぎ の場合には法律が契約書を作るように特別 の規定をおき、契約の書面化を要請 しています。
① 農地の賃貸借契約のいわゆる小作契 約 は、これを文書にしてその写しを農 業委員会に提出しなければなりません(農 地法二五条)。
② 建築エ事請負契約を結ぶときには、契 約書を作成し、工事内容、請負代金、着工 期などの事項を記載しなければなりません (建設業法一九条)。
③ 割賦販売法に定める指定商品について 月賦販売契約を結ぶときは、売主から買主 に対して、割賦販売価格や、商品の引渡時期などを記載した書面を交付しなければな りません(割賦販売法四条)
訪問販売、連鎖販売、特定継続的役務提 供等の取引でも書面の作成が「特定商取引 に関する法律」で要求されています。
④ 借地借家法では、次のタイプの契約に ついては、契約書の作成を要求しています。
1 存続期間を50年以上とする定期借地 権設定契約(22条)
2 事業用定期借地権設定契約(公正証書 によらねばならない 23条)
3 更新の無い定期建物賃貸借契約(38 条)
4 取壊予定の建物の賃貸借契約(39条)
以上の場合には、例外的に、契約書の作成が要請されていますので、注意が必要です。
これらはともに、弱者保護を考慮しての要請ということになります。