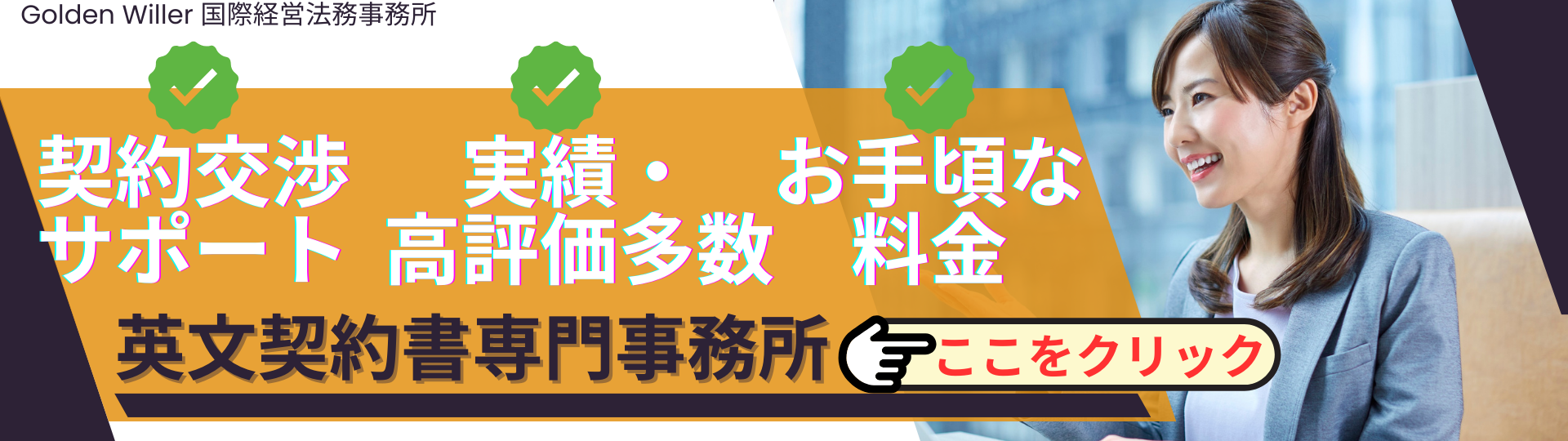契約書の違約金の条項をわかりやすく解説します
違約金の条項とは
違約金は、契約の当事者が契約内容に違反したときに、裁判によらずに、相手方に対して一定の金額を支払うことをあらかじめ予定しておく条項です。
民法では、損害賠償額の予定と言います(民法420条)。
一般的に、損害賠償額というのは、紛争が裁判所に持ち込まれたとしても、なかなか判定の難しいものです。
逸失利益(当事者の不履行によって失った利益)の計算は比較的簡単に行えますが、将来の得べかりし利益(将来発生するとみられる損害)については、その判別にはどうしても推測が伴うので、仕方がないともいえます。
そこで、この違約金の条項を定めておくと、裁判所でも難しい得べかりし利益分の損害が容易に補填できると言うわけです。
本条項例としましては、「売主または買主が不履行の場合は、代金 額の10パーセントを違約金として相手方 に支払うものとする」
また、「違約金 として金OO円を支払う」等があります。
違約金の条項の機能
契約を締結し、契約書を作成しても、相手方が履行してくれなければ、裁判等で強制が必要ですので、契約書は、その証拠として機能します。
ですが、裁判でも、本当の意味での損害回復は難しいものです。
そのような場合に、有効な手段として契約書の違約金の条項があります。
この契約書の違約金の条項を利用することで、上記のような場合に、裁判を回避し、損害額の回復を容易にすることが出来ます。
遅延についての違約金の条項
当事者が自己の債務を履行しなかった時には、上記の条項で良いのですが、履行が遅れているときにも、違約金の条項が有効です。
いわゆる遅延損害金です。
不履行が継続している間、一日OO円や、年率O%の遅延損害金を支払う等です。
違約金の額
違約金の額は、当事者が合意すればいくらでもさだめることが可能です。
しかし、あまりにも適当でない場合には、公序良俗違反として無効と判断される場合があります(民法90条)。
特別法では、一般消 費者保護の観点から、業者側から請求する 違約金の額に制限を設けています。
その一つとして、宅地建物取引業者自身 が売主となって、宅地建物を売買する契約 の場合は、二Oパーセント以内という制限 が設けられています(宅地建物取引業法三 八条)。