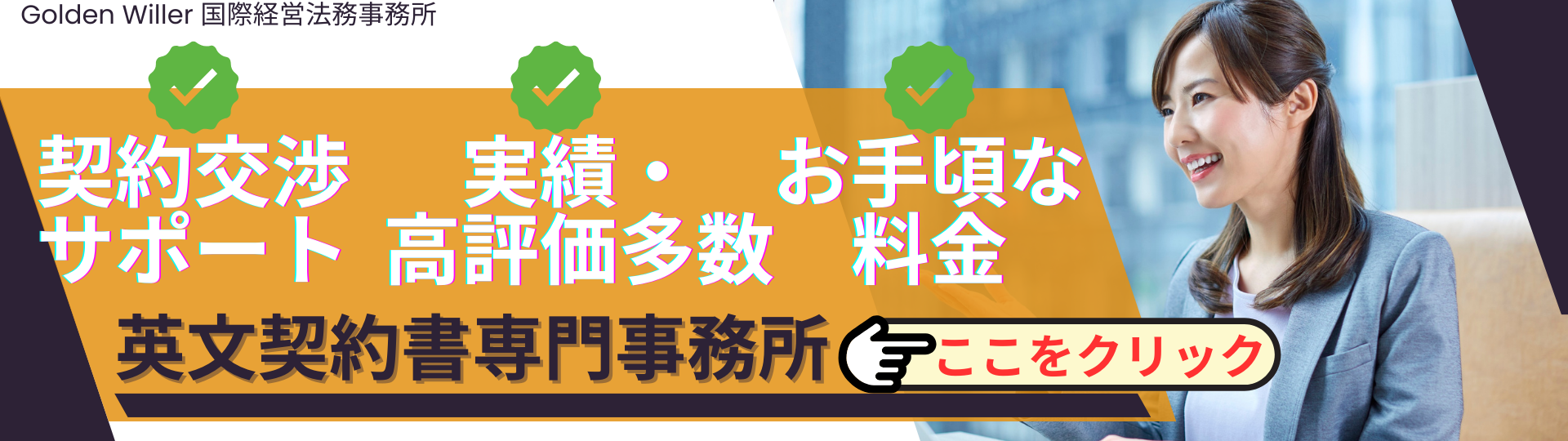英文契約書での英米法の損害賠償の内容、定め方、注意点、日本法との相違等をわかりやすく解説します
英米法上の損害賠償請求の内容と日本の民法での損害賠償請求の相違について
日本の民法であれば、契約成立後の債務不履行についての救済は、「損害賠償請求」「履行の強制」「契約解除」が通常と言えます。
他方、英米法の契約成立後の債務不履行についての救済は、コモンローでの「損害賠償請求」が原則となり、「契約解除」は一定の場合(実行困難性、目的達成不能等)にできるのみです。
上記の「契約解除」ですが、少し詳しく言いますと、債務不履行の責任が問われなくなる結果、契約が終了するという経過をたどります。
例えば、目的物の引き渡し債務が不可能になった場合等に、相手方の金銭支払債務が「不履行」とはならず、契約が終了するという場面を言います。
英米法では債務の不履行に債務者の帰責事由が必要とならないのが原則ですが(絶対責任)、上記の契約解除の例は本来であれば債務者の帰責事由の有無に関わらず損害賠償によって解決する絶対責任の例外と言えます。
ですので、債務不履行にならない場合は上記の例外等ですので、英文契約書上で「不可抗力」等の場合に不履行の免責条項を定めておく必要があります。
対して、日本の民法では損害賠償請求には債務者の帰責事由が原則必要です。
ですので、日本の契約書上では「不可抗力」は記載しなくても問題ないと言えます。
「履行の強制」も認められますが、これはエクイティによる例外となります。
そして、損害賠償請求できる利益は、「履行利益」「信頼利益」「現状回復利益」となっていますが、「履行利益」が損害賠償請求の中心となります。
その「履行利益」には、「通常損害」と「特別損害」がありますが、通常損害は裁判所でも立証が容易であり、当事者の予見が不要ですので契約書に定めなくても良いと考えますが、通常損害については当事者の予見が必要で裁判所も立証が困難ですので、契約書に詳細に規定する必要があるといえます。
なぜ英米法上の損害賠償請求はこのようになっているか
この問題は英米法上、債務の不履行をどのように考えるかに端を発します。
日本では債務の不履行は良くないことと捉えられますが、英米法上では債務の不履行は当然であると考えられるのが多数意見と言えます。
それは、債務の履行、不履行は債務者の自由意思であり、また目的物をより高く交換するために元の契約を履行しないことは社会経済的価値が高いから、と考えているからです。
これは、「契約を破る自由」と言い換えられます。
このことから、債務不履行の損害賠償には帰責事由が必要なく、また相手方を「履行があった状態」にすることが公平だということから履行利益の賠償が原則となります。
このように、「契約を破る自由」は英米法独自の概念でありますので、この概念から英米法の損害賠償請求を理解する必要があるといえます。