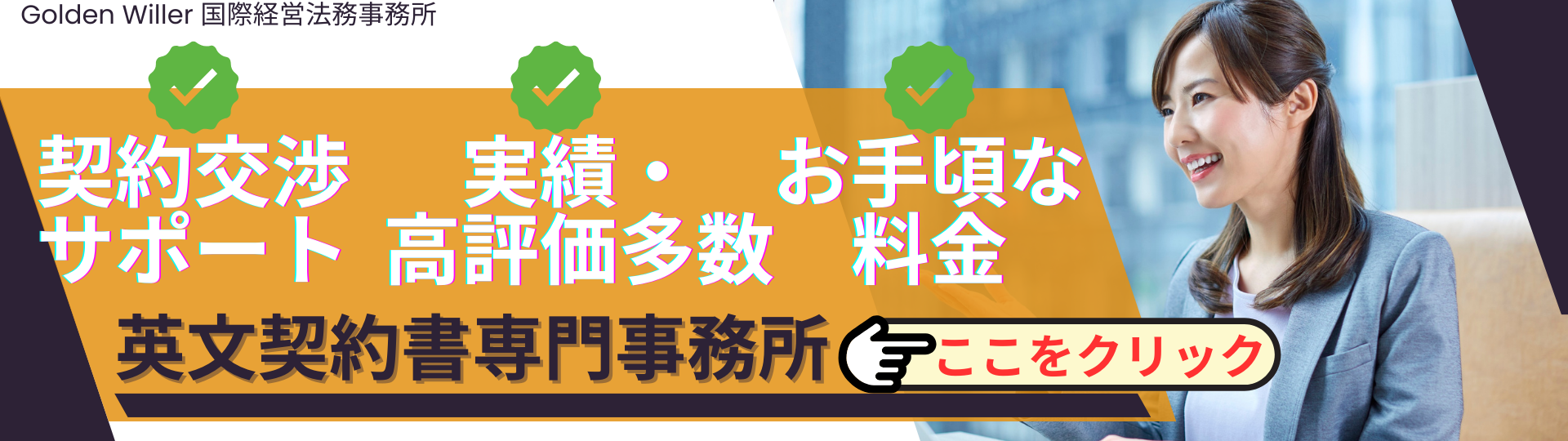法律家でもわかりにくい強行規定,任意規定の違いをわかりやすく解説します
強行規定,任意規定の違い
日本の民法は、民法91条で、「公の秩序に関しない規定の排除」がてきることを定めています。
「強行規定」とは、「公の秩序に関する規定」をいい、対して、「任意規定」とは、「公の秩序に関しない規定」を言います。
少し難しい概念ですが、以下詳しく見ていきましょう。
強行規定
強行規定と任意規定という概念は、初めて聞く方にとっては少し難しいものと思われます。
強行規定とは、民法91条の「公の秩序に関する規定(公序良俗)」を言い、これに反する当事者間の取り決めは、無効となります。
例えば、マンションの賃貸契約で、借主に子供が生まれた場合には、賃貸借契約を解除できると定めることは、公序良俗に反するので、無効となります。
なぜなら、賃借人は弱い立場に置かれがちなので、賃借人の保護というものは「公の秩序」に当たるからです。
このように、強行規定は主に「弱者保護」を目的としています。
ですので、上記と同様に「消費者保護」や「従業員の保護」の規定は強行規定となります。
任意規定
任意規定というのは、強行規定と取締規定以外の規定を言います。
取締規定というのは、行政目的や刑事目的での規制を言います。
ですので、法律に規定されている内容が、任意規定であれば、当事者が自由に取り決めることが出来ます。
どちらが原則的ルールか
これについては、契約自由の原則という概念の説明が不可欠となります。
契約自由の原則とは、基本的に契約内容、形式についてはすべて当事者の自由にあるというものです。
これは、自由な経済活動が行われることによって、経済が活発化し、発展することによって全ての人に利益になるという、古代ローマ時代からの重要な哲学に基づくものです。
ですので、契約は当事者の自由な意思に基づくことが大原則であり、国家等がそこに介入することは最小限になされなければなりません。
よって、任意規定が原則ということになり、社会通念上、許容されないと思われる規定を排除するという消極的意味合いで、強行規定が存在します。
例えば、使用者と雇用者との関係を規律する規定は、雇用者から過度に搾取されないように、労働基準法によって規律されています。
これらは、強行規定が多いです。
対して、民法は、市民間の取引に資する法律ですので、任意規定が圧倒的です。
契約書に規定すると無効になる条項
契約書に書くとその条項が無効になる、あるいは、契約全体が無効になるリ スクがある条項には具体的にどのような条項があるでしょうか。
① 販売代理店契約書に「販売店は・供給業者から購入した本件製品 を供給業者が指定する価格未満の価格で第三者へ再販売してはならない。」
と いういわゆる、再販売価格の拘束規定があった場合には、自由競争を阻害す る不公正取引に該当するので、独占禁止法違反で当該規定が無効とされます。
②外国為替管理法で禁止されている対象国ヘタイから再輸出するこ とを契約上規定している、買い主であるタイの企業との売買契約は、取引自体 が違法性を帯びることになり,禁止対象国への輸出行為が達成されなければ 契約の目的を達成しないと解釈されますので、当該売買契約全体が無効にな ると解釈されます。