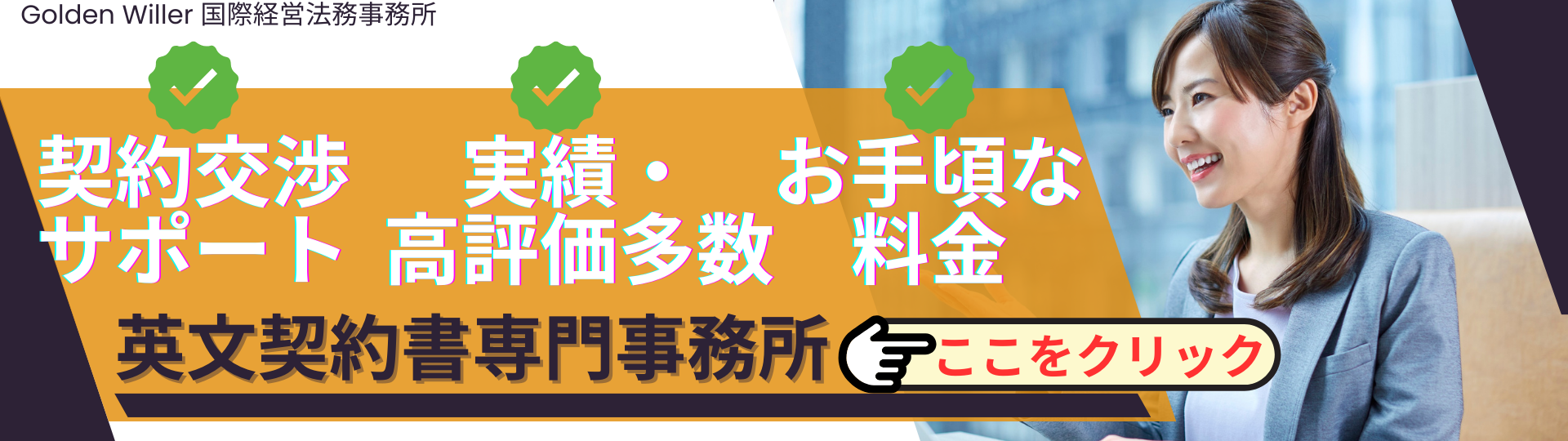IT契約書の法的問題点をわかりやすく解説します
ITビジネスと契約書の重要性
ITビジネスに契約書がなぜ重要なのでしょうか。
以下に考察していきたいと思います。
民法で保護されにくい
まず、ITビジネス上の契約では、日本の民法上での契約類型に当てはまらない契約が少なくないことから、法律により重要な権利が保護できないことが多々あります。
通常の売買契約等であれば、民法のような法律が契約当事者の重要な権利を保護してくれるので、契約書は「商品に関すること」と「対価に関すること」のみで、債務不履行の損害賠償についてや商品に欠陥があった場合の対応等を記載しなくても取引において大きな支障はないと言えます。
ITビジネスモデルは多種多様
ですが、ITビジネスはIoTやモバイル端末により、多種多様な製品・サービスとして多岐に渡り新しいビジネスモデルが誕生しています。
そこでは、民法が想定する古い取引である買主(ユーザ)と売主(ベンダ)の二当事者で完結する契約ではなく、これに加えて、システム開発では、コンサル業者やデータセンター、ベンダの下請けやパッケージベンダー等が有機的に関連し一連の契約関係を形成します(エコシステム)ので、損害賠償の範囲等、法律による保護の基準が明確となりません(システム開発が完了できなかった場合に、ユーザーがベンダにどこまでの損害を問えるかが問題となります)。
判例上の解決基準が少ない
これに関連して、ソフトウエア・システム開発委託契約で多々問題になることですが、完成したソフトウエアに欠陥があった場合、これが民法上の「瑕疵」(民法570条)に当たるかが法律や判例上の基準が無いのが現状です。
また、クラウドサービス利用契約においては、SaaS(software as a service)やPaaS(platform as a service)などのマシンベースによるサービスがあり、このような新しいサービス上の紛争を解決する判例そのものの蓄積もありません。
製品の特殊性
上記に加えて、ソフトウエア・システム開発・ライセンス・クラウドサービス利用等のITビジネスの対象となる商品は「有体物」ではなく、形のない「無体物」ですので、プログラムやデータそれ自体は所有権の対象とはなりません(民法85条)。
ですので、著作権法や不正競争防止法等で保護されなければ、法律による保護はありません。
どのように権利を保護し、紛争を適切に解決できるか
では、どうすれば契約当事者の重要な権利を確実に保護することが出来るのでしょうか。
それは、本ページのタイトルにあります通り「契約書」に全ての重要な権利を適切に記載することです。
ソフトウエア・システム開発・ライセンス・クラウドサービス利用等の契約書に全ての重要な権利を記載すれば、紛争を未然に防止し、裁判官はその記載を基に判断する必要がありますので、紛争が生じたとしても思わぬ損害や多額の賠償を防ぐことが出来ます。
ITビジネスでの契約書作成方法
ITビジネスでの契約書を適切に作成するには、多角的な視点が必要となります。
当該ソフトウエア・システム開発・ライセンス・クラウドサービス利用契約等のビジネスモデルを把握し、また精通し、複数当事者からなる契約関係を分析することにより、適切に利害関係を認識したうえで、契約書を作成する必要があると言えます。